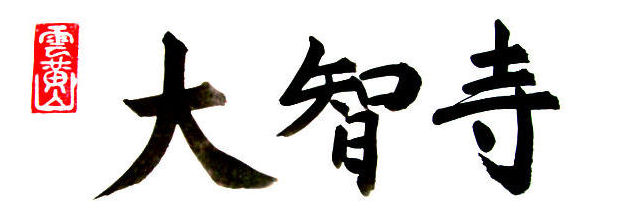松尾芭蕉俳句を全国に広め、俳論に秀でた各務支考
○松尾芭蕉の十哲の一人、美濃派俳諧の始祖各務支考は1665年
山県郡北野村西山の村瀬家に生まれました
が幼少期に母を亡くし、姉の嫁ぎ先に入籍し、各務の姓となりました。
その後、6才~19才までを大智寺第4世の弟子として大智寺に住居しました。
○当時の大智寺には多数の修業僧や小僧さんが生活しており、
支考もまたその分に応じた仕事を続けつつ、文字・漢籍の知識を修得し
人間支考の基礎が養われたようです。
○19才で還俗し、元禄3年芭蕉と出会ってからも、大智寺で得た知識が大いに役立ち、芭蕉に重宝がられたとのことです。
○なお、大智寺には支考がこの地に戻ってからの住居(獅子庵)が現存しております。
簡素で味わい深い後年の支考が偲ばれます。
○昭和9年に河東碧梧桐夫妻が、また、翌昭和10年荻原井水泉も獅子庵を訪れているとか…
大智寺発各務支考、岐阜に~支考ロードを!~
○平成22年、「獅子吼」創刊90周年・・・支考を祖として、波乱の歴史をかい潜り
守り続けられた「獅子門」俳誌「獅子吼」
○美濃を越え、全国行脚に果敢に挑んだ
各務支考・・・
にも関わらず、俳句史に於いて軽んじられてきた彼の足跡を現在に蘇らせ
後世に伝播すべく
支考ロード”が提案されています 彼
| 獅子庵 |
梅花仏 |
 |
 |
平成23年11月6日より この獅子庵補修工事が始まりました。
獅子庵は、支考が北野に戻ってからの建築として、290年余の歳月を経ていますから
現在まで、保っていたのが、不思議かもしれません。
この度、やっと解体復元工事の夢が叶いました
皆々様の御尽力御協力のおかげと感謝申し上げます
ページトップへ
芭蕉晩年の"かるみ"の俳風や平明な日常的世界を重視した支考は、
芭蕉没後、都会派の江戸座に対し、美濃派を立机した。
田舎蕉門と言われつつも、近畿・北陸・中国・四国・九州へを継承した
蕉門美濃派を伝播し、長寿結社40社を誕生させている。
行脚日数は 芭蕉=1.82ヶ月?/年 支考=2.26ヶ月/年
この時代に、地方から地方へ行脚して俳句を広めていった支考は、目的地での人との交流交渉術セールス術をもち、更に、"夜話"という一種のイベントを企画運営する能力に長けていたと思われる。又、1日36句の歌仙形式の連句を1巻24句へ、連句のマニュアルをも定めるアイデアを持っていた。
このような能力は当時の文人からは偏見の視線を浴びたであろうが、現在の文芸もまた"アイデア・セールス・イベント"によって世に送り出されている一面を見れば、支考の手法は確かに画期的なものであったようだ。
今日、全国津々浦々に育っている俳句サークルの、最初の種蒔をしたのが各務支考である。
◎ 各務支考のエピソード
その① 支考の名前 あれ?これ?
旅先や作品によって名前を変更し、数多くの変名を持っていたそうです。
野盤子 東華坊 西華坊 獅子老人 桃花仙人 黄色山老人など…
その② 支考の著書あまた
書く事、旅をする事が彼の人生だったようで、多数の書物を残しています。
葛の松原 芭蕉翁追善記 俳諧古今抄 東華集 西華集 三匹猿など…
その③ 芭蕉と伴に
弟子入り以来、薪水の労、旅のお伴、最期の看病、遺言状代筆、葬儀、法要などを師の為に執り行った支考は、それだけ芭蕉と信頼関係にあったとも考えられています。
その④ 支考の生前葬
「俺はもう死んだ」と死んだフリをして、別の名前で本を出版したこともあったようです。堅物俳人と思いきや、ちょっとお茶目で風狂な人だったのですね。
その⑤ 獅子庵での生活
「我、机を離れなば この世の限りと思うべし」
その⑥ 支考が命名~桑名名物・時雨蛤~
『東海道名所図絵』(1797)に「初冬の頃 美味なるゆゑ 時雨蛤の名あり 留まりにて製す」
とある。江戸の将軍へ献上されるのが慣例となっていた桑名宿の煮蛤を
「時雨蛤」と命名したのは桑名市史のよると芭蕉の高弟各務支考といわている。
時の俳人佐々部岱山が今一色の業者から命名を頼まれ師匠の支考に相談したところ
「十月より製し候事故、時雨蛤と命題し・・・・・」として名づけたということです
◎ 支考の作品
牛叱る 声に鴫たつ 夕べかな
山の端の 月見や岐阜は 十三夜
魂棚に 油火細し 我ごとく /
船頭の 耳のとうさよ 桃の花
歌書よりも 軍書にかなし 吉野山
うらやましう うつくしうなりて ちる紅葉
食堂に 雀啼くなり 夕時雨
野に死なば 野を見て思へ 草の花
腹立てる 人にぬめくる なまこ哉
気みじかし 夜ながし 老いの物狂ひ
娑婆にひとり 淋しさ思へ 置き火鉢
◎ 支考の略歴
寛文5年(1665)・・山県郡北野村西山。村瀬家の次男として誕生
6才~19才・・・・大智寺第四世の弟子となる
元禄3年(1690)・・・芭蕉門下となる
正徳元年(1711)・・この地に獅子庵をむすぶ
享保16年(1732)・・2月7日、67才で没
「美濃派俳句資料館」も御参照下さい
ページトップへ
獅子門って何かな?……「獅子吼」って何かな?
| 獅子庵 |
梅花仏 |

|

|
各務支考の別号の獅子老人にちなんで付けられた俳句のグループ名です。
美濃を本拠に活動し、歴代宗匠に美濃在住者が多いので、美濃派ともいわれます。
伝統を踏まえつつ、現代に根ざす俳句と
連句の創作研究を続けています。
芭蕉忌や支考忌には伝承の正式俳諧(しょうしきはいかい)を興行しています。
「獅子吼」とは、獅子門の方々が投稿した俳句や各務支考の事
その他俳句まめ知識や会員通信などが掲載された月刊誌の名前です。
大正8年に創刊し、昭和23年から月刊誌になっています。
ページトップへ
支考の句~月刊「獅子吼」より~
各務支考の句・ある日ある時
| 1月号 | 正月の月夜はうれし見はせねど | 享保16年正月の月夜と言われ心浮き立つも
見る気力すら無かったのか…この年2月支考67歳で世を去る |
| 〃 | 大根はこなたに雪のいぶき山 | 雪を頂いた伊吹山を背景に大根の袈掛
大いなる美濃平野 |
| 〃 | 若菜摘手や袖縁の紅の色 | 若菜の緑に袖口の紅色…雅な姫とも違う
童乙女の柔らかな香 |
| 〃 | 念仏と豆腐たふとし老いの春 | さて、支考何才の春であろうか?老いての後は
信仰と食…うれしさも中くらいなりおらだ春…も近い |
| 2月号 | 鶯の蹴立によるか梅の雪 | 鶯が飛び立ったためか、梅の雪はらりと落ちる。二重季語はダメなんて! |
| 〃 | 是までか是までかとてはるのゆき | 是でおわりかな~と思われつつも又もや雪とは言え
ほんのり春の色。 |
| 〃 | しら玉や梅のつぼみも一包ミ | 春は別れの季節…近世なら尚、惜別の心計り知れず
はなむけに梅の一枝 |
| 〃 | はなのさく木はいそがしき二月哉 | はなのさく・いそがしき.と平仮名散らし
春の目覚めを感じる句 |
| 3月号 | 2004年令和5年「獅子吼」3月号に支考俳句掲載なし。 | 支考の句何処と尋ぬ春の風 |
| 〃 | うき恋にたえでや猫の盗喰 | もし「たえてや」ならばこの猫いじらしくも滑稽
「たえでや」は支考目線の滑稽さ… |
| 〃 | うぐいすの合羽やほしき雨の音 | 春の雨音が聞こえて来そうな句。美声も披露できず
せめて合羽でも…温かな情を醸す春のひとコマ |
| 〃 | 早わらびの何かは握る袖の内 | 何かを握りしめるような早蕨の姿、ギュッと握った物は?
ホラねっ!やっぱり袖の中のそれでした |
| 4月号 | 駒とめてみたきは花の御嵩哉 | 初めて俳人国騅にあった時の挨拶句とは言え
駒と桜のほのぼのとした風景が無に浮かぶ句では。。。 |
| 〃 | 九牛が毛桃の花や稲荷前 | 突如9頭の牛が出てびっくり!が、九牛云々は「毛桃」の
枕詞的なもの?稲荷前にも句が飛び出す |
| 〃 | 小田の二字首にかけてや鳴蛙 | 初めは?鳴く蛙の姿が浮かんでナ~ルほど…
手をついて歌申しあぐる蛙かな…と並びそうだ |
| 〃 | 媒(なかうど)は先へ行きけり弥生山 | 近隣の嫁ぎ先へ歩む花嫁行列。急く仲人に
文欽高島田は追いつけず…過ぎし弥生 |
| 5月号 | 筍の露あかつきの山寒し | 暁に竹藪に立てば、露しげくうそ寒い静けさが沁みる |
| 〃 | 鶯をいなせて竹の落葉かな | いなせ~とは?春から夏にかけてザワザワト竹落葉
旅の哀歓すら感じる |
| 〃 | 夏はまだ浅黄に啼や松の鹿 | 中央の「に」、いくつかの意味を含んでリズムを整え
初夏に子鹿の啼く声を添える |
| 〃 | 一声や空に花さくほとゝぎす | 時鳥の一声、それは空いっぱいに咲いた花だ!
聴覚が視覚を覚ます大花火の一句一句 |
| 6月号 | 昼がほに敷寝の袖や貝遊び | 敷寝の袖…はて?砂浜に袖汚しつつ、昼顔の傍、美なる貝を手にした? |
| 〃 | ゆりの花生ければあちらむきたがる | 全く言い得て妙である。恣意的に動けば
それを見越しているかのようにプイと横向く、可愛さもある |
| 〃 | 世の耳を聞かでたふとし時鳥 | 馬耳東風と時鳥の一声
悟りの境地を象徴するかのように… |
| 〃 | 五月雨の夕日や見せて出雲崎 | 五月雨の夕日で…旅先での夕餉の一時が
イメージされる。支考の笑顔が見える |
| 7月号 | ちり込めて昼寝を埋む笹葉哉 | 笹の葉に埋められての昼寝…そこに蛇も蟻もないのが俳句だろうか |
| 〃 | 関の灯のあなたこなたを夕涼み | 関は下関、美濃からは遥かに遠い関門海峡を眺めつつの夕涼み |
| 〃 | 村雨の雫や木々に飛ぶほたる | 雨湿りの間にゆらりと飛ぶ蛍、乱舞する蛍…幻想的な夜の一幕 |
| 〃 | 夕晴の雲や黄色に瓜の花 | 夏の夕刻…空の黄色と大地の恵み相照らし、生命の謳歌… |
| 8月号 | 蜻蛉のあたまにとまる日向かな | 頭に止まる蜻蛉を止まるがままにしておく長閑な昼日向 |
tr>〃 | 三味線に秋まだ若し涼み舟 | 秋またっぷりなだ若し…が不愉快な残暑を打ち消し
その語自体に夏の涼を感じる |
<| 〃 | 風鈴や秋を触行(ふれゆく)市の中 | 風鈴売りの音が暑さを払い涼しさを来す、秋遠からず |
| 〃 | 仰けに寝てみれや天の川 | あおむけに、次は岐阜弁で「~mirya-」ほれ、あおむけにねてみィ~と |
| 9月 | 帆にあまる風や松吹庭の秋 | 帆にあまるで、たっぷりな豊かな風が松の庭に吹く様が見えるようだ |
| 〃 | 朝顔やゆふべの人のなき便 | 昨夜の人が亡くなったという便り、儚さは朝顔の命。
朝顔やかの人の逝く便り哉 |
| 〃 | きりぎりす啼せて寝たし籠枕 | 江戸に5つの風流あり。雪見、花見、月見、菊見、虫聞き
枕にきりぎりすの啼くを入れる…支考的発想か |
| 〃 | 名月を耳に聞夜ぞ竹の雨 | 月を耳で聞く、竹に降る雨音もそれなりに…
大雨小雨風情を感じさせる |
| 10月号 | 茸狩といふて出ばや旅姿 | 茸狩や空手で戻る騒ぎかな?の句が浮かぶ
が支考は装うばかり哉 |
| 〃 | <渋谷の柿のしぶしぶわかれ哉 | 東京渋谷ではなく福井しぶたに 別離が
渋柿に掛けられ気分上々 |
| 〃 | 船超してとべやどなたも秋の暮 | 福井は三国新保での事。俳句仲間が船で往来
あの人この人の秋の暮 |
| 〃 | 関守はゆるさぬ鳫のそら音かな | 百人一首を思い出す。雅と俳諧の粋な出逢い
支考の智恵もまた俳諧か |
| 11月号 | すげなきは酢の看板と冬の月 | 酢が「す」なら尚冬月夜がしみわたるかも… |
| 〃 | 新酒にはよき肴あり松の月 | 松にかかる月を肴に見立てたのか、旅寝の旅情か |
| 〃 | 夜にめでゝ雁も平砂の旅寝かな | 三国にて「平砂落雁」に因んで旅の情深まる |
| 〃 | 城外の鐘きこゆらむもみぢやま | 中唐の詩人張継作を知る人ぞ知る…考えさせられる |
| 12月号 | 伊吹には雪こそ見ゆれ大根引き | 濃尾平野の大地の冬の風景、大根で道をおしえけり |
| 〃 | 茶の花や是も玄旨の植残し | 玄旨とは武将で茶道を究めた細川藤孝、茶の花から故人を偲ぶ |
| 〃 | 霜月に節句もあらば水僊花 | 霜月に節句があれば、寒空に匂う水仙こそが節句の花だろう |
| 〃 | 三日月も似合に凄し冬の雲 | 冬の雲と三日月が醸す荒涼たる景色に、静寂と怪しさが重なる |
第5回獅子庵投句ポスト特選句
○獅子庵に来て払ひあふ草虱 名古屋市 山口こひな
へ
○如月の白き日差しの支考句碑 大垣市 川瀬スマ子
○風がふく踊りだしたよひがん花 岐阜市 渡辺直紀
今月の三輪句会
2025年2月
〇一人来て一人帰らむ秋の夜半 義弘
〇冬構えさりとてどこぞをどうしやう 義弘
〇しみじみと鍬を打ちたり冬夕焼 義弘
〇山眠る動かぬものがそのままに 義弘
〇どす利かせ唸る黒猫路地寒し 義弘
以上の句を最期に義弘氏は ながの旅路につかれ、三輪句会は終焉を迎えました。
いくつ読めるかな?~難語・脳トレ~全問正解で俳句王?
まずは……蛞蝓(?)に塩ひとつまみほどの悔い……答えは欄外デス
| Q. | 鴨足草 | 蓼 | 一叢 | 薔薇 | 棘 | 晩稲 | 通草 | 稲架 | 藺草 | 牛膝 | 金縷梅 |
| A. | ゆきのした | たで | ひとむら | そうび | おどろ | おくて | あけび | はさ | いぐさ | いのこずち | まんさく |
| Q. | 水洟 | 転寝 | 眩暈 | 跣足 | 碇星 | 杓文字 | 熟睡 | 焜炉 | 轆轤 | 禊 | 蔕 |
| A. | みずばな | うたたね | めまい | はだし | いかりぼし | しゃもじ | うまい | こんろ | ろくろ | みそぎ | へた |
| Q. | 就中 | 喘ぐ | 掠める | 零れる | 劈く | 縋る | 鏤める | 強面 | 現世 | 手遊び | 徐 |
| A. | なかんづく | あえぐ | かすめる | こぼれる | つんざく | すがる | ちりばめる | こわもて | うつしよ | てすさび | おもむろ |
| Q. | 欲る | 撥釣瓶喘ぐ | 幣辛夷 | 傀儡 | 屯する | 詐り | 恣 | 独活 | 四阿 | 金糸雀 | 忍冬 |
| A. | ほる | <ェtd>はねつるべしでこぶし | かいらい | たむろするく | いつわり | ほしいまま | うど | あずまや | カナリヤ | すいかずら |
ェ
答え=ナメクジ
ページトップへ
☆岐阜市文芸祭作品募集 案内
俳句2首まで
募集期間 令和7年6月1日~7月15日
問合せ先 岐阜市文芸祭事務局
☆獅子庵清掃 ご協力
日時 7月19日(土)午後1時30分より獅子庵現地集合
☆第22回東花賞作品募集 案内
獅子句会員 20句
募集期間 令和7年9月1日~9月15日
☆支考研究の第一人者 堀切実先生 新刊紹介
〇『芭蕉を受け継ぐ現代俳人』~季語と取り合わせの文化~
〇ぺりかん社 3,500円+税
おまけ~獅子門道統系譜~
①松尾芭蕉―②各務支考―③仙石―④田中五竹坊→2派に分かれる
(以哉派)⑤安田以哉坊―⑥大野是什坊―……35益井一鴎…36川井一白
(再和派)⑤河村再和坊―⑥佐々木森々庵……24田内盤古庵…25丹羽玄々庵
|昭和48年合同 37各務於菟―38沢田蘆月―39国島十雨―40伊藤白雲―41大野鵠士
ページトップへ
|
© 2008 Copyright DAICHIJI. All right reserved.
|
 |